建築物の安全性を確保する上で、火災の早期発見と避難誘導は最も重要な要素の一つです。
自動火災報知設備は、この重要な役割を担う設備として、消防法により一定規模以上の建物に設置が義務付けられています。
しかし、自動火災報知設備の設計・施工において、多くの方が「警戒区域の分割方法」「感知器の設置間隔」「発信機の必要台数」などの具体的な基準について悩まれることがあります。
本記事では、自動火災報知設備の基本構成から設置基準、実務上の注意点まで、建築設備の設計・施工に携わる方にとって必要な知識を3分で理解できるよう、分かりやすく解説いたします。
1. はじめに
自動火災報知設備とは?
自動火災報知設備は、火災の早期発見と通報を行う設備です。
火災が発生すると、感知器が煙や熱を検知し、受信機に信号を送信します。受信機は建物内の人々に火災の発生を知らせ、避難を促します。
なぜ必要なのか
建築物では、火災の早期発見が人命と財産を守るために重要です。
自動火災報知設備は、消防法により一定規模以上の建物に設置が義務付けられています。
火災の早期発見により、避難時間の確保と初期消火が可能になり、被害を最小限に抑えることができます。
2. 自動火災報知設備の基本構成
自動火災報知設備は、主に受信機、感知器、発信機の3つの機器で構成されています。
それぞれの役割を理解することで、システム全体の仕組みが分かります。
受信機(P型・R型の違い)
受信機は、感知器や発信機からの信号を受信し、火災の発生を建物内に知らせる中心的な機器です。
P型受信機
- 特徴: 火災信号や設備作動信号を受信
- 用途: 中小規模建物向け
- 機能: 基本的な火災報知機能
P型受信機は、比較的小さな建物で使用される基本的な受信機です。
火災信号を受信すると、音響装置や表示灯を作動させて火災の発生を知らせます。
R型受信機
- 特徴: Record型、液晶表示画面付き
- 用途: 大規模建物向け
- 機能: 詳細な情報表示、記録機能
R型受信機は、大規模な建物で使用される高機能な受信機です。
液晶画面で火災の発生場所や詳細情報を表示し、記録機能も備えています。
感知器(煙感知器・熱感知器の種類と特徴)
感知器は、火災の初期段階で発生する煙や熱を検知する機器です。
火災の種類や設置場所に応じて、適切な感知器を選択する必要があります。
煙感知器
煙感知器は、火災時に発生する煙を検知します。
煙が感知器に入ると、光の散乱や遮光により火災を検知します。
- 光電式スポット型: 煙による光の散乱を検知
- 分離型: 送光部と受光部が分離
- 設置種別: 露出型、埋め込み型、プチタイプ
熱感知器
熱感知器は、火災による温度上昇を検知します。
煙が発生しにくい場所や、煙感知器が誤作動しやすい場所で使用されます。
- 差動式スポット型: 温度上昇率を検知
- 差動式分布型: 広範囲の温度変化を検知
- 定温式スポット型: 一定温度に達すると作動
- 設置種別: 防湿型、防水型、防爆型
発信機(P型・R型の違い)
発信機は、人が手動で火災を通報するための機器です。
避難経路など、人が集まる場所に設置されます。
P型発信器
- 1級: 1回線用
- 2級: 2回線用
- 3級: 3回線用
R型発信器
- 特徴: 大規模建物用
- 機能: アドレス設定機能付き
3. 設置基準と警戒区域
警戒区域の定義と基準
自動火災報知設備を設置する際は、建物をいくつかの警戒区域に分けて計画します。
警戒区域は、火災が発生した際に、どの範囲で火災が発生したかを特定するための区域です。
消防法第8条第1項による基準:
- 階数: 2つ以上の階にわたらないこと
- 面積: 1つの警戒区域の面積は600㎡以下
- 距離: 一辺の長さは50m以下
これらの基準により、火災の発生場所を正確に特定し、適切な避難誘導が可能になります。
【計算例1】警戒区域の分割数の計算
問題: ある建物の1フロアが900㎡の場合、警戒区域はいくつ必要か?
計算手順:
- 1区域の面積上限: 600㎡
- 必要区域数: 900 ÷ 600 = 1.5
- 小数点以下切り上げ: 2区域必要
答え: 2区域に分割する必要があります
解説: 1区域の面積上限600㎡を超えるため、2つ以上の警戒区域に分割する必要があります。
これにより、火災の発生場所を正確に特定できるようになります。
4. 感知器の設置ポイント
感知器の設置方法・種別
感知器は、火災を早期に発見するために、適切な場所に適切な間隔で設置する必要があります。
設置間隔が広すぎると火災の検知が遅れ、狭すぎるとコストが高くなります。
設置間隔の基準
- 煙感知器: 天井高さ3m以下で最大間隔9m
- 熱感知器: 天井高さ3m以下で最大間隔7m
設置種別
- 露出型: 天井面に直接設置
- 埋め込み型: 天井に埋め込み設置
- プチタイプ: 小型で目立たない設置
【計算例2】感知器の設置間隔の計算
問題: 天井高さ3m、煙感知器の設置間隔の上限は?
計算手順:
- 天井高さ: 3m
- 煙感知器の最大間隔: 9m
- 設置間隔上限: 9m
答え: 最大間隔9m
解説: 感知器同士の距離が9mを超えないように配置する必要があります。
これにより、火災の早期発見が可能になります。
5. 発信機・表示灯・音響装置の設置
発信機の設置基準
発信機は、人が火災を発見した際に手動で通報するための機器です。
避難経路など、人が集まる場所に設置し、誰でも操作できる高さに設置します。
- 設置位置: 各階の避難経路に設置
- 設置高さ: 床面から1.2m以上1.5m以下
- 設置間隔: 50m以内ごとに設置
【計算例3】発信機の必要台数の計算
問題: 延べ面積1200㎡の建物で、発信機は何台必要か?
計算手順:
- 1台でカバー可能面積: 600㎡
- 必要台数: 1200 ÷ 600 = 2台
- 各警戒区域に最低1台設置
答え: 2台
解説: 各警戒区域ごとに最低1台の発信機を設置する必要があります。
これにより、どの区域でも火災を通報できるようになります。
表示灯・音響装置
表示灯と音響装置は、火災の発生を建物内の人々に知らせるための機器です。
- 表示灯: 火災報知区域を表示
- 音響装置: 火災報知音を発報
- 設置位置: 避難経路に沿って設置
6. 連動設備と実務上の注意点
屋内消火栓等との連動
自動火災報知設備は、他の消火設備と連動して動作します。
火災報知機が作動すると、自動的に消火設備も作動し、初期消火を開始します。
- 連動機能: 火災報知と同時に消火設備を作動
- 連動設備: 屋内消火栓、スプリンクラー設備
- 作動条件: 火災報知機の作動により自動連動
実務での設計・施工・保守のポイント
設計時の注意点
- 警戒区域の適切な分割
- 感知器の設置間隔の確認
- 避難経路の確保
施工時の注意点
- 配線の接続確認
- 感知器の設置角度
- 発信機の操作確認
保守時の注意点
- 定期点検の実施
- 感知器の清掃
- 動作確認の実施
7. まとめ
重要ポイントの再確認
自動火災報知設備の設計・施工において、以下のポイントが重要です:
- 警戒区域: 600㎡以下、50m以下、2階以下
- 感知器: 煙感知器9m間隔、熱感知器7m間隔
- 発信機: 各警戒区域に最低1台
- 連動設備: 消火設備との連動機能
現場・試験で役立つ知識
建築設備の設計・施工に携わる方にとって、以下の知識が重要です:
- 計算: 警戒区域の分割、感知器の設置間隔、発信機の台数
- 法令: 消防法第8条第1項の基準
- 実務: 設計・施工・保守の各段階での注意点
自動火災報知設備は、火災の早期発見と避難誘導に重要な設備です。
基本構成と設置基準を理解し、適切な設計・施工・保守を行うことで、建物の安全性を確保できます。
関連記事:
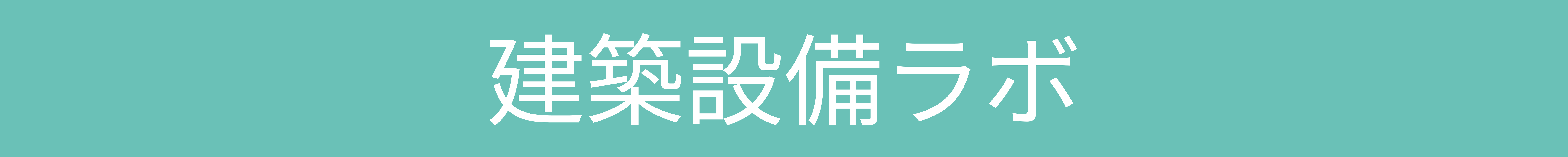
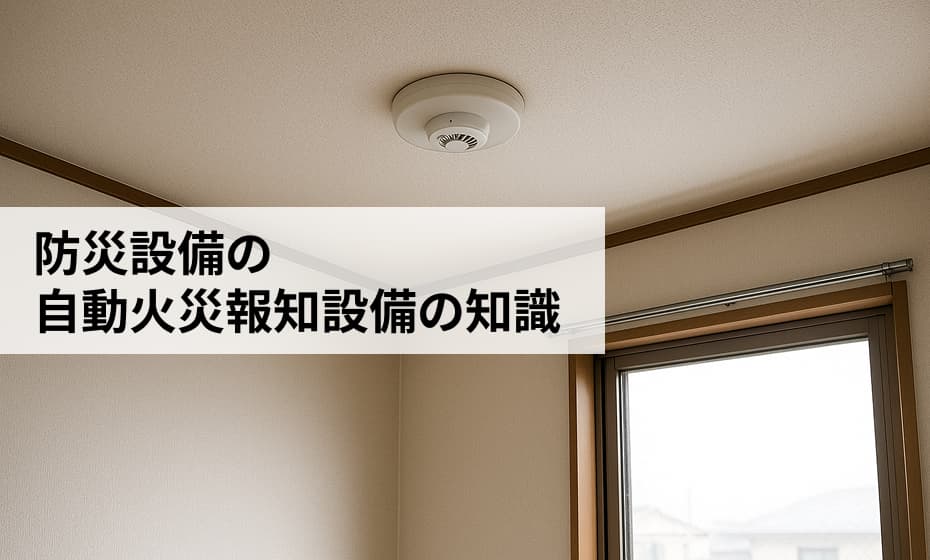








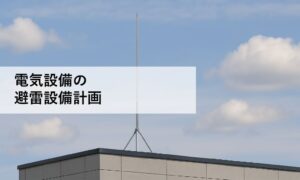



コメント・質問