3分でわかる設備の計画では、建築設備に関する計画について、3分で理解できる簡単な解説を行います。
雷による被害は、建物や電気設備だけでなく、人命にも及ぶ深刻なものです。
特に近年は気象の激甚化により、都市部や高層建築における雷対策の重要性が高まっています。
この記事では、避雷設備の基礎から計算方法、実際の例題までを丁寧に解説し、安全な建築設計・設備設計に役立つ情報をお届けします。
避雷設備とは?
避雷設備とは、建物に雷が落ちた際、その電流を安全に地面へ流すための設備です。
雷による火災や感電、機器の損傷などを防ぐ目的で設置されます。
- 建物の構造体や屋根への直撃を防止
- 電気設備や通信機器への過電圧障害を防ぐ
- 人体への感電事故のリスク軽減
法的には「建築基準法施行令 第126条の5」に基づき、高さ20mを超える建築物などに設置が義務づけられています。
避雷設備の種類と設計手法
避雷設備は大きく以下の3つの設計手法と、3つの構成要素によって成り立ちます。
保護範囲の設計手法
避雷設備がどの範囲まで保護するかを評価するために、以下の3つの方法が用いられます
保護角法(Angle Method)
- 避雷針から一定角度(一般に60°)で広がる円錐形の範囲内を保護対象とする。
- 高さ20m以下の一般建築物に最もよく用いられる手法。
回転球体法(Rolling Sphere Method)
- 半径20~60m程度の仮想球を建物に転がし、雷撃が到達しうる箇所を特定。
- 国際規格IEC 62305に準拠。高層建築や重要施設向け。
メッシュ法(Mesh Method)
- 半径20~60m程度の仮想球を建物に転がし、雷撃が到達しうる箇所を特定。
- 国際規格IEC 62305に準拠。高層建築や重要施設向け。
主な構成要素
- 受雷部(雷を受ける部分)
- 突針(避雷針)式:金属製の棒を建物上部に設置
- 架空地線式:建物上空にワイヤを張って広範囲を保護
- メッシュ式:屋上に金属メッシュを設置し全体を覆う
- 引下げ導線(雷電流を地面に導く)
- 建物の外壁などに沿って垂直に敷設される導体
- 接地極(地面に電流を逃がす)
- 地中に埋められた銅板やアース棒など
避雷設備の計算方法(保護角法)
今回はポピュラーな「保護角法」による計算を紹介します。
保護範囲の半径(r)の計算式
r ≒ h × tanθ
計算式の凡例
r:保護される水平距離(m)
h:避雷針の高さ(m)
Q:風量[m3/h]
θ:保護角(一般に60度)
避雷設備の計算例問題とその解答
問題
屋上の中心に避雷針を設置する際に、屋上の中心から端までの距離が10mある場合、保護角60°を適用するには避雷針の高さhは最低どれくらい必要か?
解答
r ≒ h × 1.732
10 ≦ h × 1.732
h ≧ 10 / 1.732 ≒ 5.77
避雷針の高さは 5.8m以上 が必要
まとめ
避雷設備は、建物の安全を確保する上で欠かせない要素です。
- 設計には「保護角法」「回転球体法」「メッシュ法」の3手法がある
- 構成要素は「受雷部」「引下げ導線」「接地極」
- 高さ20m以下の一般建築物には保護角法がよく用いられる
- 避雷針の高さを逆算して、建物全体が保護範囲に入るよう設計する
雷害リスクを減らし、安全な建築物を設計・運用するために、適切な避雷設備の導入は極めて重要です。
本記事は簡単に計画方法をまとめております。
より詳細に算出することも可能です。
電気設備に関する、詳しくは以下の書籍をご確認ください。
資格関連の記事もあります。ぜひチェックしてください!
- 建築設備士に合格するためのコツと勉強方法【学科は独学、製図は講習会で合格です】
- 一級建築士試験の資格学校4選について解説【おすすめはスタディングとTACです】
- 設備設計一級建築士の修了考査通過に向けた学習方法を解説【過去問を入手しよう】
以上、避雷設備の基礎知識と計算方法【3分でわかる設備の計画】でした。
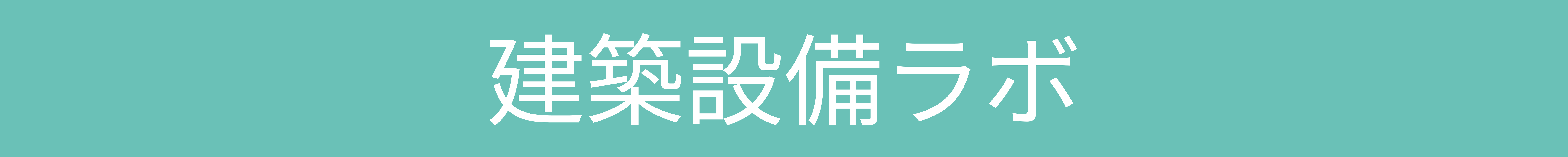
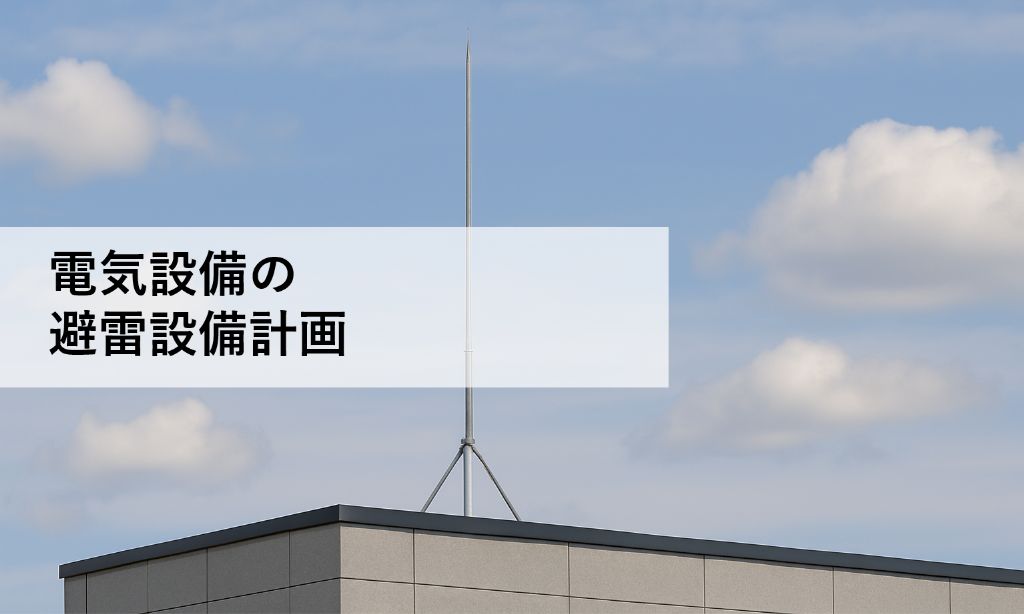






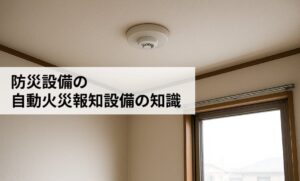






コメント・質問